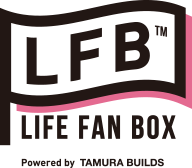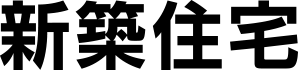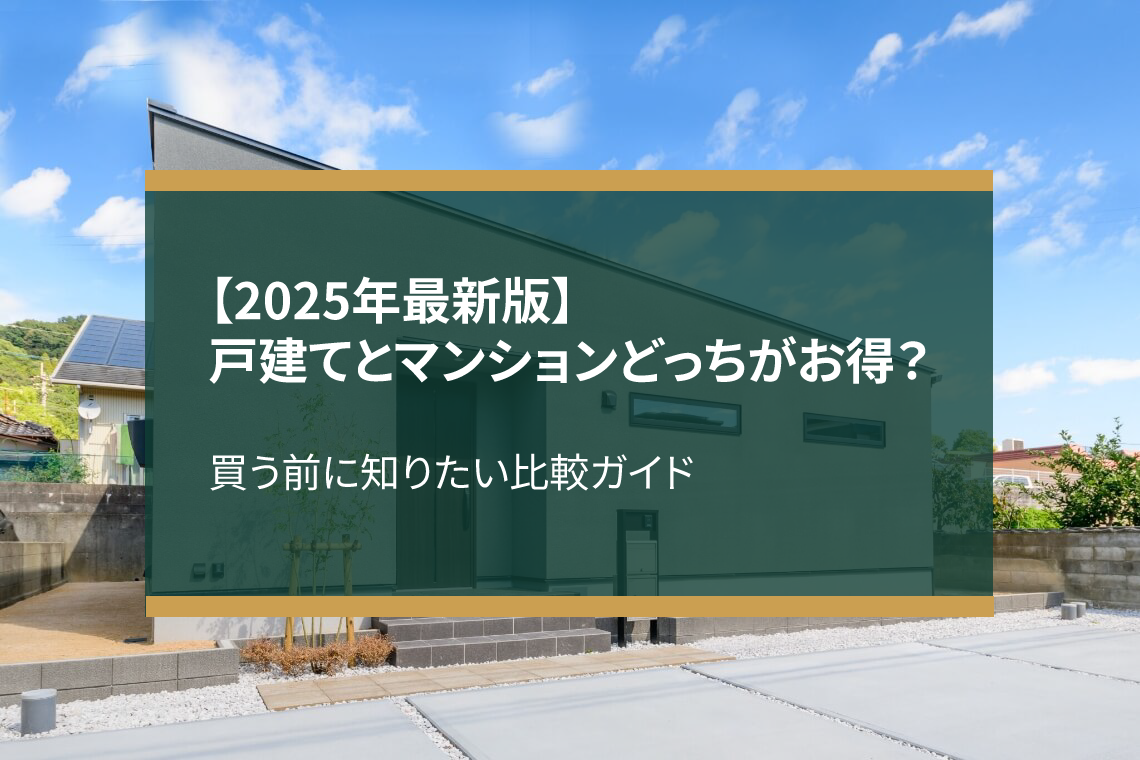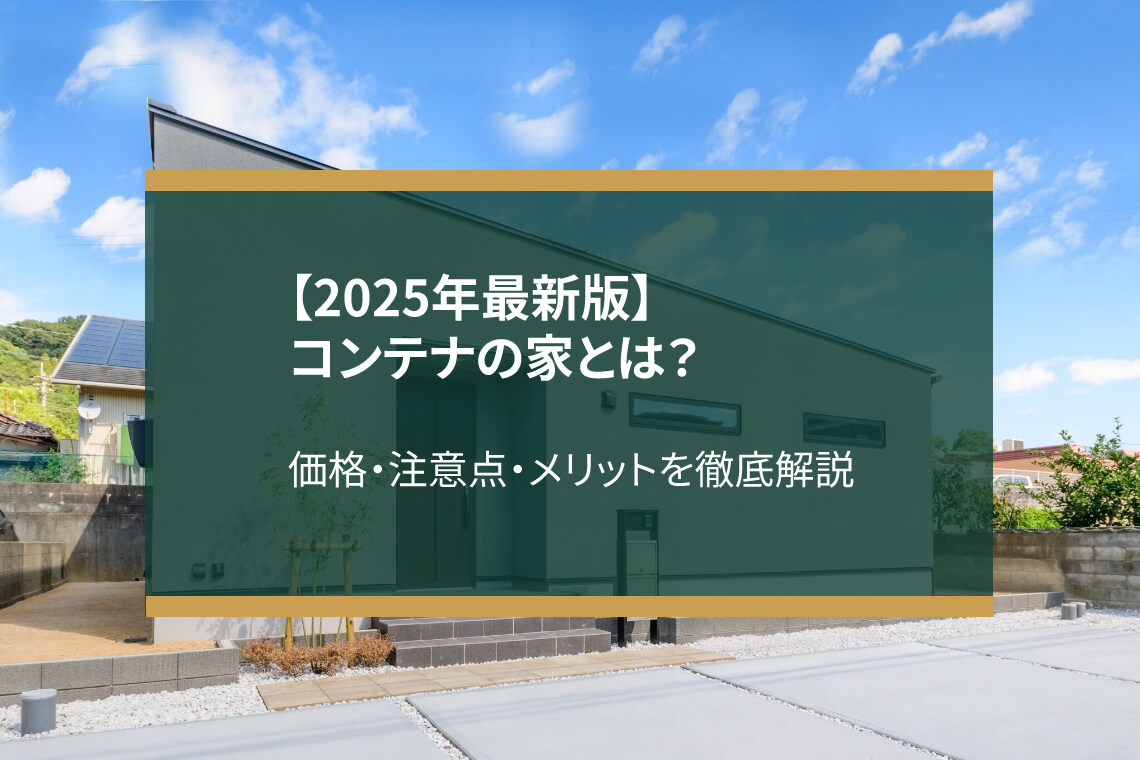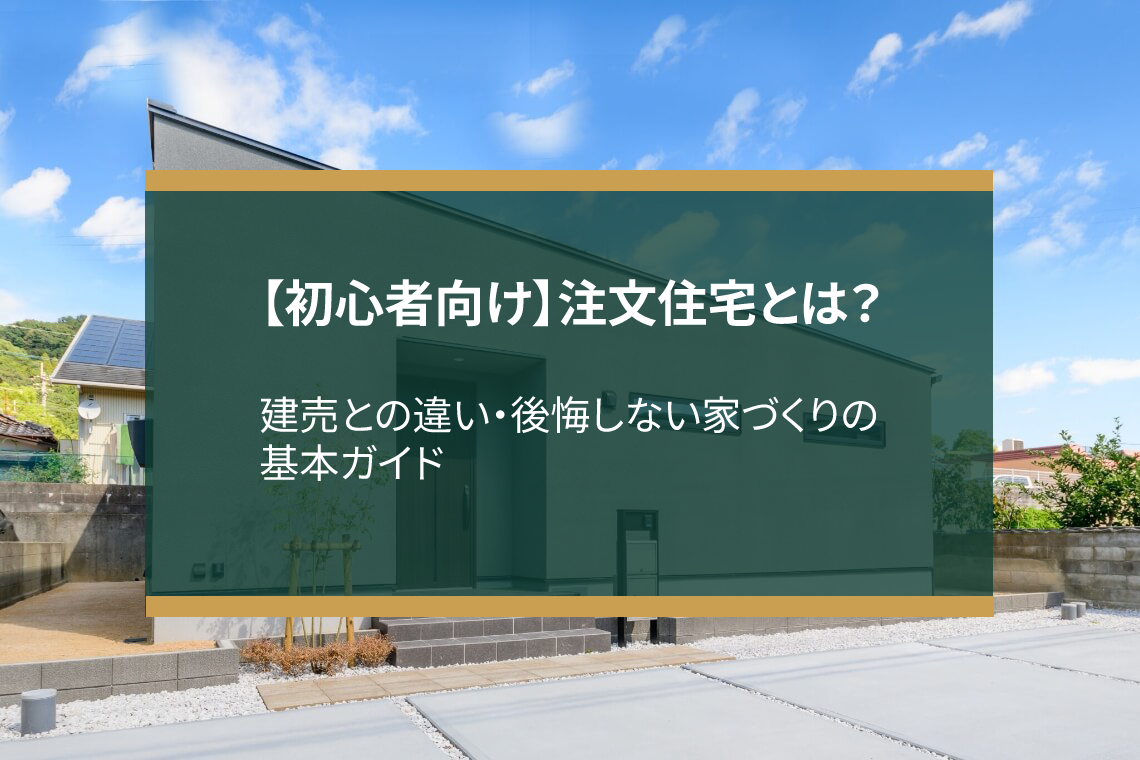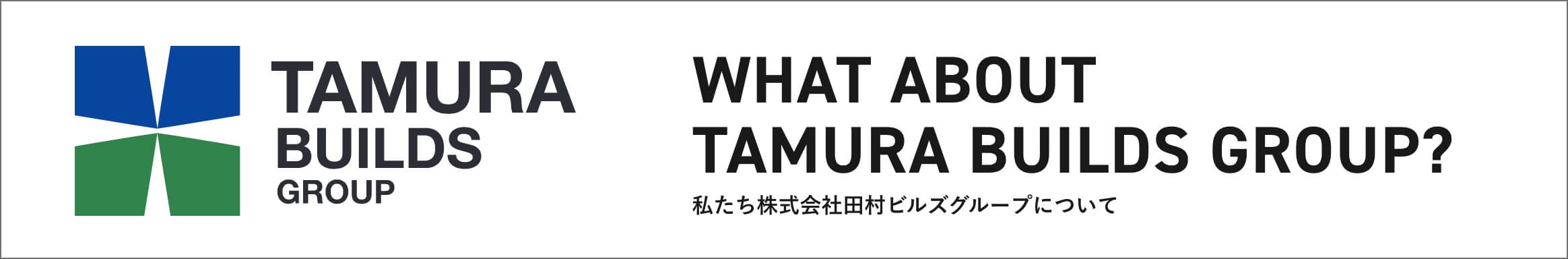NEWS
お知らせ
- COLUMN
- 2025.7.18
【完全解説】耐震等級とは?等級1・2・3の違いと選び方|家族を守る安心な住まいの基準
【完全解説】耐震等級とは?等級1・2・3の違いと選び方|家族を守る安心な住まいの基準
「地震に強い家がいい」と思っていても、実際にどのくらいの強さを持つ住宅を選べばよいのか、判断に迷う方は多いのではないでしょうか?
そんなときに参考にしたいのが「耐震等級」です。これは住宅の地震への強さを1〜3の数値で評価する制度で、**建築基準法を超えた「構造の見える化」**とも言える指標です。
特に日本は地震大国。今後30年以内に大地震が発生する確率は、地域によっては70%を超えるとも言われています。だからこそ、家づくりにおいて“耐震性能”の確認は絶対に避けて通れません。
このコラムでは、注文住宅や建売住宅、中古住宅の購入を検討されている方、さらにはリフォーム・減税・助成金を検討している方に向けて、耐震等級の仕組み・違い・選び方・経済的メリットをわかりやすく解説いたします。
将来の安心と後悔しない家づくりのために、ぜひ最後までご覧ください。
1. 耐震等級とは?住宅の耐震性能を示す3段階の基準
耐震等級とは、「住宅性能表示制度」において建物の地震に対する強さを数値で示した指標です。この制度は国土交通省が定めるもので、建物の構造の安全性を「耐震等級1〜3」の3段階で表しています。
具体的には、地震が発生した際にどれだけ建物が損傷せず耐えられるかを、地震力に対する建物の強さで評価します。等級が上がるごとに建物の構造体が強化され、より大きな地震にも耐えうる設計となっているのが特徴です。
耐震等級を取得するには、設計段階で耐震性を確保したうえで、第三者機関の評価を受ける必要があります。そのため、建築基準法を満たすだけでなく、信頼できる構造計算と性能証明がセットで求められる制度なのです。
2. 耐震等級1・2・3の違いを具体的に比較
それぞれの等級で求められる性能は、以下の通りです。
等級1(最低基準)
建築基準法に定められた基準を満たす等級です。震度6強〜7程度の地震でも、建物が「倒壊・崩壊しない」ことを前提にしていますが、大きな損傷や機能喪失はあり得ます。つまり、一度の大地震には耐えるものの、「その後も住み続けられるか」は不透明なレベルです。
等級2(避難所レベル)
等級1の1.25倍の耐震性能が求められます。震災時の避難所として使われる学校や公民館などと同等の強さで、震度6〜7の地震でも損傷を抑えながら安全性を保ちます。家族の安全と、ある程度の居住継続性を両立したレベルです。
等級3(最高レベル)
等級1の1.5倍の耐震性能が必要です。消防署や警察署など、災害時の拠点となる施設にも求められるレベルで、建物の変形や損傷を最小限に抑えつつ、大地震後も居住可能な性能を持ちます。注文住宅や地震リスクの高い地域では、ほぼ標準的な選択肢となりつつあります。
3. なぜ「耐震等級3」が推奨されるのか?
等級3が推奨される理由は、単に地震に強いからというだけではありません。近年の大規模地震において、等級3の住宅がほぼ無傷で残った実例が多数報告されており、建築基準法の最低基準(等級1)との差が明らかになっています。
たとえば、2016年の熊本地震では、耐震等級3の住宅のほとんどが軽微な損傷のみで済みました。一方、等級1の住宅では、部分的な崩壊や大きなひび割れなどの被害が多発しました。
さらに、等級3を取得しておくことで、地震保険料が最大50%割引になる、将来的に建物の資産価値が落ちにくい、といった経済的メリットも得られます。これらの要素を総合的に考えると、「等級3」はコスト以上の価値を提供する基準といえるのです。
4. 耐震等級が高いと得られる5つのメリット
1. 地震に強く、家族の命を守る
大地震の際にも倒壊リスクが極めて低く、安全な避難時間や生活の継続性が確保されます。
2. 地震保険料が安くなる
耐震等級2以上で保険料が30%〜50%割引に。等級3なら最も割引率が高くなります。
3. 住宅ローン審査で有利になるケースも
金融機関によっては、耐震性能が高いことで金利や審査面で優遇されることがあります。
4. 資産価値が高く、売却時も有利
住宅購入者は「地震に強い家」を求める傾向が強く、等級が記載された住宅は中古市場でも人気です。
5. 助成金・税制優遇の対象になる
長期優良住宅・こどもエコすまい支援事業などの対象になるケースがあり、初期費用を抑えられます。
5. 「長期優良住宅」と「耐震等級」の関係
長期優良住宅とは、国が定めた「長く安心して住み続けられる住宅」に与えられる認定制度です。その認定条件の一つが、耐震等級2以上であること。
つまり、耐震等級1の住宅では、どんなに他の性能が高くても、長期優良住宅には認定されません。
長期優良住宅の認定を受けることで、以下のような具体的なメリットがあります:
・固定資産税の軽減:5年間→最大7年間軽減
・住宅ローン減税の限度額UP
・登録免許税や不動産取得税の優遇
・自治体の補助金が活用できる場合もあり
そのため、「高性能な住宅=耐震等級2以上」といっても過言ではありません。
6. 中古住宅・建売住宅でも確認すべき耐震等級
耐震等級の重要性は、新築住宅に限った話ではありません。中古住宅や建売住宅を選ぶ際にも、等級の有無・レベルは重要なチェックポイントです。
【中古住宅の場合】
・築年数に注目:1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は、旧耐震基準のため等級が付いていないことが多く、耐震改修が必要です。
・証明書を確認:評価機関の発行する「耐震等級評価書」や性能表示をチェックしましょう。
【建売住宅の場合】
・パンフレットの記載を鵜呑みにしない:等級3と書かれていても、「設計段階のみ」の評価である場合があり、実際の施工内容とズレがあるケースも。
・完成済物件なら第三者評価の有無を確認:構造計算・性能評価書があれば信頼性が高いです。
7. 耐震等級取得に必要な費用と設計ポイント
耐震等級を取得するには、構造計算を実施し、第三者評価機関による認定を受ける必要があります。具体的には、下記の流れとなります。
・建築士が**構造設計(許容応力度計算など)**を行う
・建物のプランや構造を図面化し、評価機関に提出
・認定後、評価証明書が発行される
【費用の目安】
・耐震等級2:約10万円前後
・耐震等級3:10〜30万円(設計料含む)
また、等級3を取得するためには、柱や耐力壁の配置バランス、地盤調査結果に応じた基礎構造の最適化などが求められます。結果的に、一般的な設計よりも5〜10%程度コストが上がるケースもあります。
8. 耐震等級に関するよくある質問Q&A
Q1. 耐震等級3を取っていれば、地震の被害はゼロですか?
A1. 耐震等級3は非常に強い基準ですが、「絶対に無被害」とは言えません。ただし、震度7クラスの地震でも建物の倒壊を防ぎ、命を守る可能性が高いと実証されています。
Q2. 中古住宅でも耐震等級を上げられますか?
A2. 可能ですが、全面的な耐震改修が必要になります。費用は数百万円になることもあるため、事前の診断が重要です。
Q3. 実際にどの等級を選べばよいですか?
A3. 基本的には等級3がおすすめです。地震リスクが高い地域や、建物を将来的に売却・継承したい方には特に適しています。
9. 【無料で相談できます】安全な家づくりをサポートします
耐震等級を取得するかどうか、どの等級を選ぶかは、専門的な知識と判断が必要です。当社では、住宅性能に精通したスタッフが、お客様のご要望・ご予算・地域特性をふまえて最適な耐震設計プランをご提案しています。
「まだ検討段階だけど話だけ聞いてみたい」という方も、お気軽にご相談ください。
10. まとめ|耐震等級は、家族の未来を守るための基準です
家族が毎日を安心して過ごせる住まいとは、目に見えない部分――つまり構造や性能がしっかりしている住宅です。
耐震等級はその性能を「見える化」する重要な基準であり、家を選ぶ際の最も基本的かつ重要な判断材料です。
もし、どの等級が最適か迷っているなら、まずは専門家に相談してみましょう。
大切な住まいに、後悔のない選択をしていただくために、私たちが全力でサポートいたします。
11. LFB新築住宅では
LFB新築住宅では、お客様一人ひとりのニーズに合わせた家づくりをサポートしています。高品質な建材を使用し、耐震性・断熱性に優れた住宅を提供しています。また、充実のアフターサービスで、お客様の安心・安全な暮らしをサポートします。