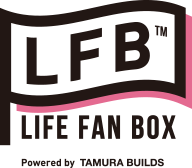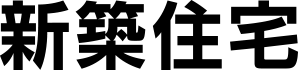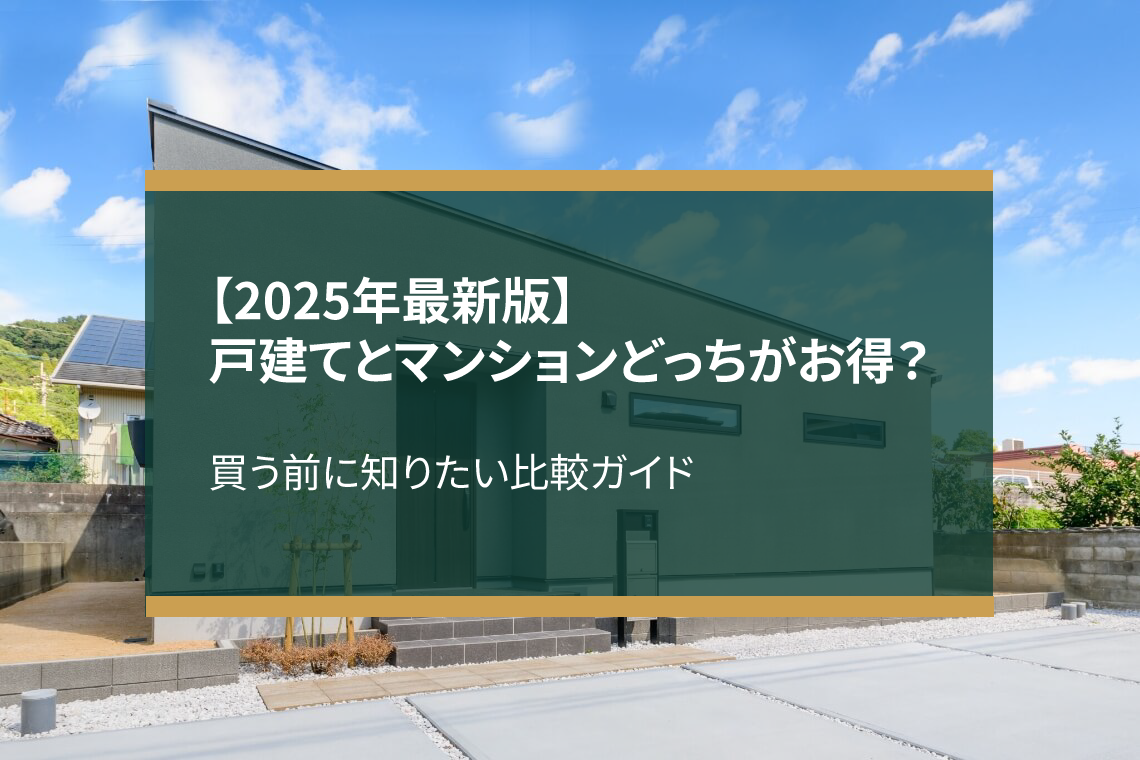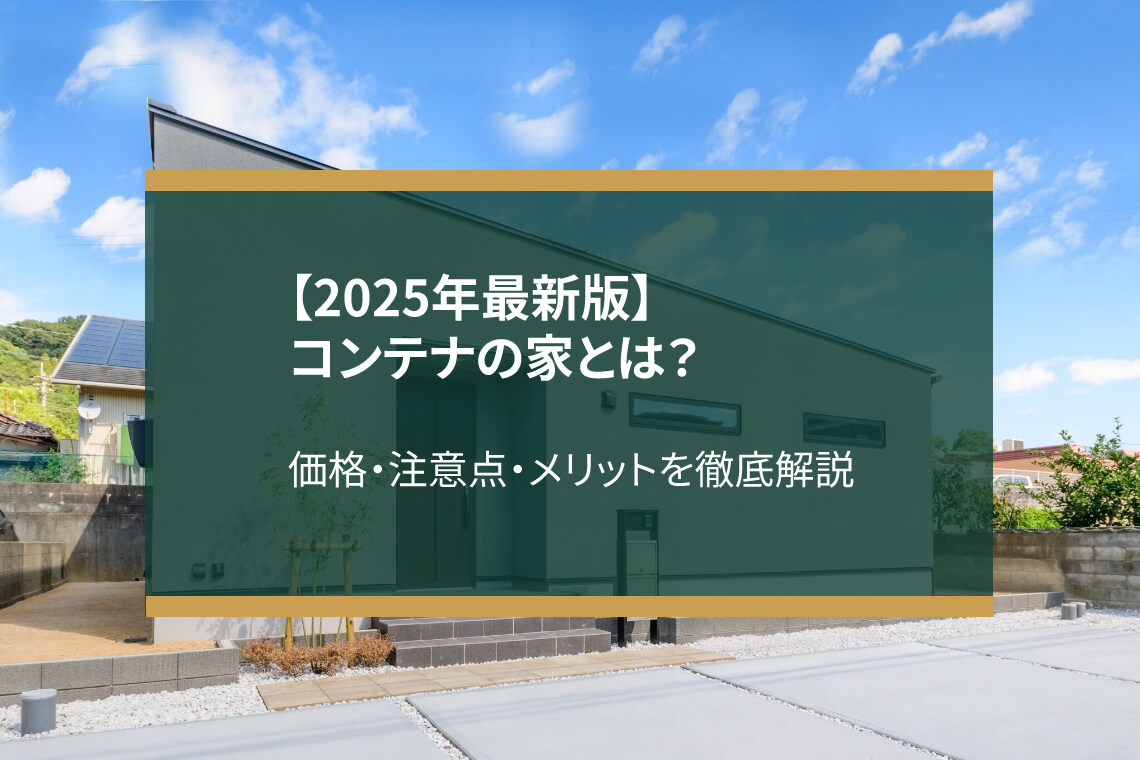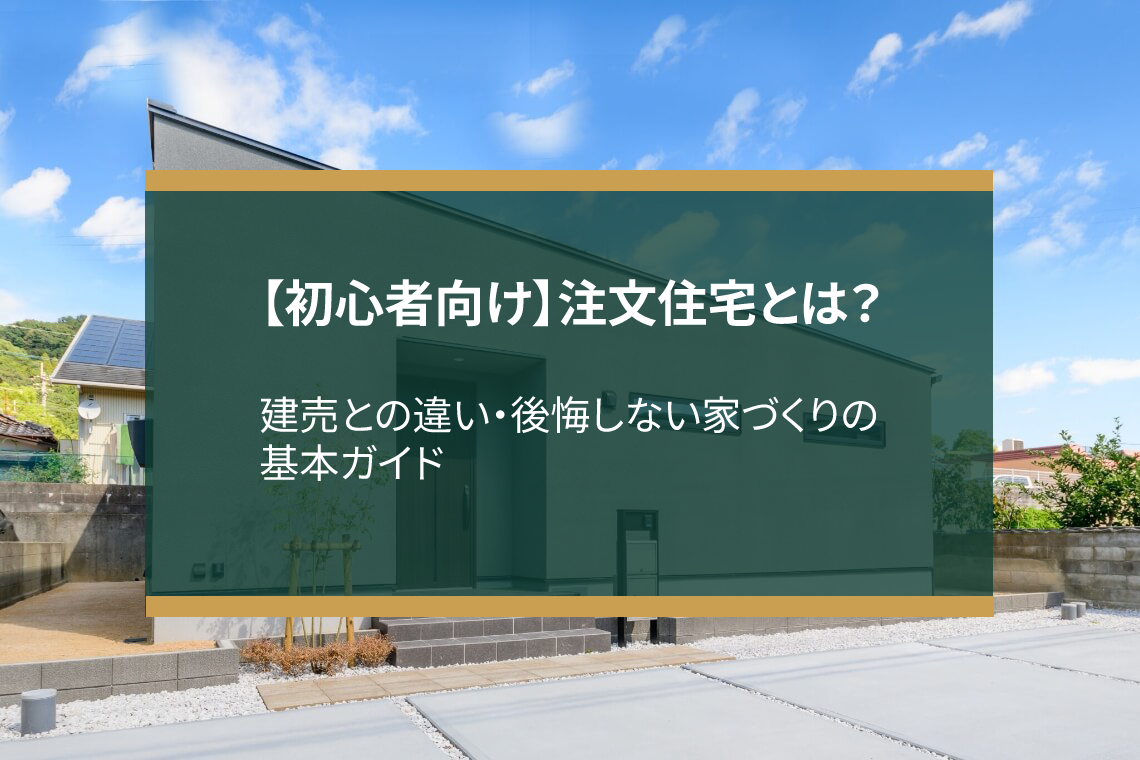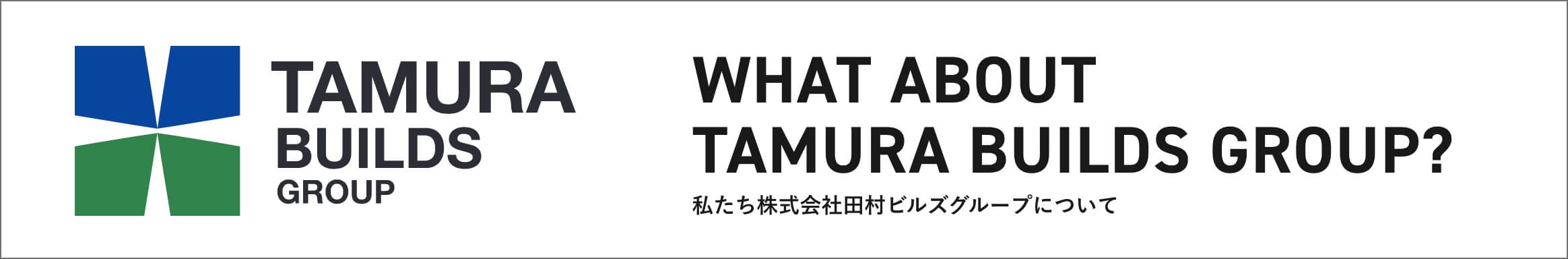NEWS
お知らせ
- COLUMN
- 2025.7.18
家を建てると補助金がもらえる?2025年最新の補助制度と活用ポイントを徹底解説
家を建てると補助金がもらえる?2025年最新の補助制度と活用ポイントを徹底解説
「家を建てる 補助金」で調べる方の多くは、「マイホームの夢を叶えたいけど費用が不安…」と悩まれているのではないでしょうか。
実は今、国や自治体による“住宅取得支援”が充実しており、条件を満たせば数十万円~100万円単位の補助金が受け取れることもあります。
特に子育て世帯や共働き夫婦、親からの支援を受けて家を建てる50~60代の方など、**「今がチャンス」**といえる制度が多数あります。
この記事では、家を建てる時にもらえる補助金の種類や条件、2025年最新情報、実際に補助金を受け取るまでの流れをわかりやすくご紹介します。
記事の最後では、「補助金を活用して賢く家を建てたい」という方に向けて、無料相談やモデルハウスのご案内もしています。ぜひ最後までご覧ください。
1. 家を建てると補助金がもらえるって本当?
「家を建てる=補助金がもらえる」と聞いても、最初は半信半疑の方が多いかもしれません。しかし、国・地方自治体ともに住宅取得支援に積極的で、一定の条件を満たせば、補助金や助成金を受け取ることができます。
たとえば、2025年度に継続されている「子育てエコホーム支援事業」では、子育て世帯や若年夫婦世帯が長期優良住宅などの高性能住宅を建てることで、最大100万円の補助金が支給されます。
さらに、住宅の性能だけでなく、建築エリアや家族構成(例:三世代同居)などに応じて、地域独自の補助金が上乗せされることもあります。
特に補助金は「返済不要」である点が最大の魅力です。うまく活用すれば、住宅取得費の一部を実質無料でまかなうことができ、建築費の負担軽減につながります。
2. 2025年最新版|家を建てる時に使える主な補助金制度一覧
以下は2025年時点で活用可能な主な補助制度です(※申請受付状況は要確認)。
| 補助制度名 | 補助額 | 対象となる条件 |
|---|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | 最大100万円 | 18歳未満の子どもがいる/夫婦のいずれかが39歳以下など |
| 地域型住宅グリーン化事業 | 30~100万円 | 長期優良住宅やZEH仕様の住宅を建築 |
| 自治体の独自支援 | ~200万円 | 市町村により条件・金額が異なる |
| 移住・定住促進補助 | ~100万円 | 指定地域への転入+新築住宅建築が条件 |
| 三世代同居支援補助 | ~50万円 | キッチン・風呂・トイレなどを複数設置し同居 |
※上記以外にも各自治体で細かな補助が用意されていますので、事前確認が重要です。
3.【タイプ別】補助金が使える人の特徴と条件
補助金制度は世帯の年齢構成や家族形態、住宅の性能、地域などによって、受けられる内容が異なります。以下に、代表的なライフスタイル別に適用されやすい補助制度をご紹介します。
1.子育て世帯(30~40代)
18歳未満の子どもがいる家庭は、子育てエコホーム支援事業の対象になりやすく、長期優良住宅であれば100万円の補助が受けられます。また、子育て支援を重視している自治体では、**独自の加算制度(例:第2子以降はさらに10万円加算)**なども存在します。
さらに、多くの市町村で実施されている「出産・育児支援型住宅助成」では、市内の小学校区ごとに条件を設けて助成額を変える地域もあります。
2.DINKs・若年共働き世帯(20~30代)
子どもがいない世帯でも、夫婦どちらかが39歳以下であれば、若年夫婦世帯として支援対象になるケースがあります。
特に「将来的な定住を期待できる若年層の呼び込み」を目的とした補助制度は多く、地方移住+新築計画で100万円以上の補助が得られる場合もあります。
3.建売住宅と注文住宅で迷う40〜50代
この層は、所得が安定している一方で補助金対象から外れやすく、住宅の性能(長期優良・ZEHなど)で補助金を確保する戦略が有効です。
また、建売住宅の場合でも、仕様や性能が一定基準を満たしていれば補助金対象になることがあるため、「補助金対応住宅」であるかを見極めて選ぶことが重要です。
4.親からの援助や相続を活用する50〜60代
この層では、土地や資金をすでに保有しているケースが多いため、建築コスト自体を補助金で圧縮できることが大きなメリットになります。
たとえば、三世代での同居を計画している場合、水回りの複数設置に対して数十万円の補助が出る自治体もあります。また、親から資金援助を受ける場合は、住宅取得資金の贈与税非課税制度と組み合わせることで、税負担をゼロに近づけることが可能です。
4. 補助金の申請から受給までの流れ
補助金を活用するためには、あらかじめ制度のスケジュールと申請方法を理解しておくことが重要です。以下は一般的な流れです。
1. 補助金制度の確認
まずは、国交省やお住まいの自治体のウェブサイト、住宅会社の担当者などから、利用できる補助金制度の種類と条件を確認します。
特に注意すべきなのは、「補助金には事前申請が必要なものが多い」点です。
2. 対象事業者との契約
補助金の対象になる住宅は、登録された事業者によって建てられる必要があります。たとえば、「子育てエコホーム支援事業」は国に登録された事業者しか対象になりません。
3. 設計・見積書などの書類準備
申請には住宅の仕様書や設計図、本人確認書類、住民票、課税証明書などの提出が求められます。書類不備があると申請が通らない場合もあるため、専門知識のある担当者と一緒に準備を進めるのが理想です。
4. 申請手続き(事前申請が多い)
制度によっては、着工前に申請が必要な場合と、完了後に報告を提出するタイプがあります。
申請後は、審査・交付決定通知を経て、着工が可能になります。
5. 工事完了・報告・補助金振込
住宅が完成したら、完了報告書を提出し、確認がとれれば後日、指定口座に補助金が振り込まれます。補助金によっては交付後数か月かかるケースもあるため、資金計画には余裕を持つことが大切です。
5. 補助金と併用できる!住宅ローン減税・贈与非課税制度
補助金と同時に検討したいのが、税制上の優遇措置です。うまく活用することで、建築費だけでなく、住宅取得後のランニングコストも抑えることが可能です。
■ 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
一定条件を満たした住宅ローン利用者は、年末のローン残高の0.7%(上限控除額あり)を13年間にわたり所得税・住民税から控除できます。
控除額の例:
4,000万円の借入 → 年28万円の控除 × 13年 = 最大364万円
長期優良住宅やZEH住宅の場合は、控除の上限額が引き上げられるため、高性能住宅の建築+補助金+減税のトリプル効果を狙うのが賢い選択です。
■ 住宅取得等資金の贈与税非課税特例(2025年版)
親や祖父母からの住宅取得資金の贈与について、最大で1,000万円(省エネ住宅の場合)まで非課税となる特例が2025年も継続中です。
これは、生前贈与でも非課税扱いとなる制度であり、特に親世代の資金援助を前提とした家づくりでは活用価値が高いです。
注意点としては、贈与を受けた年の翌年に申告が必要なため、税理士などの専門家に相談しながら進めるのがベストです。
6. よくある質問と注意点
Q1. 補助金って家を建てた後でも申請できますか?
A1. 多くの制度では、着工前の申請が必須です。工事契約や着工後では申請自体ができなくなるケースもあるため、早期に情報収集と準備を始めましょう。
Q2. 建売住宅でも補助金はもらえますか?
A2. はい。建売住宅でも、省エネ基準や認定住宅であれば対象になります。補助金が使える建売かどうかは、販売会社に確認してください。
Q3. 補助金を受け取ると住宅ローン審査に影響しますか?
A3. 直接的な影響は少ないですが、自己資金とのバランスや契約内容により金融機関が条件変更を提示することがあります。事前に金融機関にも補助金活用の旨を伝えておくと安心です。
7. 【無料相談受付中】補助金を使って賢く家を建てるには?
補助金制度は、「知っている人だけが得をする」と言っても過言ではありません。
実際に、申請を忘れて数十万円を取り逃してしまった方、申請書類の不備で補助金を受け取れなかった方も少なくありません。
当社では、補助金制度に精通した専門スタッフが常駐しており、お客様の家族構成・住宅性能・地域条件に合った補助金制度をご提案しています。
また、住宅ローン減税や贈与税非課税の活用方法についても、資金計画の段階からアドバイスが可能です。
家づくりに関する無料相談はオンライン・対面どちらでも可能です。ぜひ一度、補助金を最大限活用できる家づくりについてご相談ください。
8. LFB新築住宅では
LFB新築住宅では、お客様一人ひとりのニーズに合わせた家づくりをサポートしています。高品質な建材を使用し、耐震性・断熱性に優れた住宅を提供しています。また、充実のアフターサービスで、お客様の安心・安全な暮らしをサポートします。